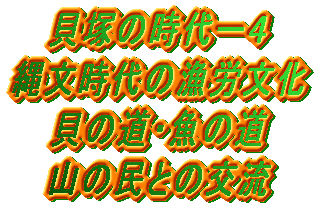
海の幸は海岸部に住む人々だけのものではなかった。縄文時代にも海の貝や魚が交換物資として内陸部に運ばれていたことを示す証拠が、近年あちこちで見つかっている。
東京湾東岸に大型貝塚が現れ始めた縄文時代中期、西岸地域(現在の東京側)では貝塚が少なく、むしろ海から10キロ以上も離れた内陸部に大規模な集落遺跡が多く形成された。このことから、この地域の人々は海産物をあまり重視していなかったと考えられていた。しかし、1996年に行われた東京都中里貝塚の調査」成果は、こうした考えを覆すとともに自給自足的な縄文社会観に修正を迫るものとなった。


東京下町低地の西縁に位置する中里貝塚は、当時の海岸に沿って帯状に広がっており、その規模は長さ1キロ、幅70〜100m、貝層の厚さは最大4〜5mに達する。これは東岸の大型貝塚十数個分に相当する規模である。
しかしながら、この貝塚は居住に適さない低湿地にあるうえ、掘って出てくるものは貝殻ばかりで、住居跡や土器・骨類などの遺物が見つからないという謎の貝塚であった。このため、本当に人間が作った「貝塚」なのか、自然の貝殻が堆積した「自然貝塚」なのかをめぐって長らく議論が交わされてきたが、今回の発掘調査によって、縄文人が当時の干潟に膨大な量の貝殻を捨て続けた結果これを埋め立てるようにして形成された貝塚であることが判明した。さらに、付近の台地上に同時代の集落跡がいくつか発見されていることから、中里貝塚はこれらの集落の人々が貝の剥き身作業を行った浜辺の水産加工場であったと推定されている。
それにしても、これほど膨大な量の貝が捕られた理由とはいったい何であろうか。付近の集落の自家消費目的だけだったとは考えにくい。
縄文中期の西岸地域では内陸部に多くの大集落が形成されるのだが、興味深いことに中里貝塚の形成期間はこれら内陸集落の盛衰と極めてよく一致しており、両者の間に密接な関連があったことを示している。
このことから、中里貝塚で剥き身にされた貝は干物などの保存食に加工され、交換物資として内陸集落へと送り出されたのではないかと考えられている。沿岸部の漁民と内陸部の狩猟・採集民とが手を結び、それぞれの産物を交換すれば、海陸の多様な資源を利用することが可能となる。
謎の巨大貝塚が形成された背景には、こうした資源利用の広域ネットワークが存在していた可能性が極めて高い。
海産物が交換物資として内陸部に送り出されていた証拠は、三内丸山遺跡でも得られている。この遺跡では様々な種類の魚骨が大量に出土しているのだが、出土する骨が頭や背骨など特定の部分に偏っているかどうかを調べてみたところ、興味深い結果が得られた。多くの種類では全身の骨がバランスよく出土しているのに対し、ブリやサバだけは頭の骨が殆ど見られず背骨が突出して多かったのである。これらの魚は夏場に網を用いて大量に捕獲されたと考えられることから、腐敗を避けるために捕獲後直ちに頭を落として内蔵を抜いて乾物に加工してから集落に持ち込んだものと見られる。このように大量生産される保存食料に関しては、余剰分が交換物資として外部に流れていたとしても不思議ではない。
実際、日本海岸から50キロほど内陸に位置する秋田県大館市池内遺跡ではサバ・ブリなどの海産魚の背骨が出土しており、海と山を結ぶ「魚の道」の存在を裏付けている。
このように、縄文時代においても海産物は海岸に暮らす人々だけの独占物ではなく、社会的なネットワークを通じて内陸域の人々にまで広くもたらされていた。海の幸は単なる食物というだけではなく、集落と集落、地域と地域とを結ぶ紐帯としての役割を担っていたのである。
中里貝塚 なかざとかいづか 東京都北区上中里にある縄文時代の国内最大級の貝塚。縄文時代中期中ごろ〜後期初めに形成された貝塚で、位置や規模から、海浜低地で貝類の加工を専門におこなった水産加工場の跡とされている。
貝層の存在は、すでに1886年(明治19)から指摘されていたが、人工的遺物が少ないことから遺跡とみなすことに疑いがもたれてきた。しかし1996年(平成8)、公園整備にともなう発掘調査の結果、貝の加工施設が発見されるとともに、長さが1km以上、幅が70〜100mもある巨大な貝塚がみつかった。貝層の厚さは最大で4.5mもあり膨大な量の貝殻である。
一般に縄文時代の貝塚は集落の中に形成され、貝殻のほかに土器、石器、獣や魚の骨などを多くふくむ。しかし中里貝塚では、それらの生活用具や、獣骨・魚骨などの食料残滓(ざんし)もほとんど出土せず、またふつうかならず周囲に発見される竪穴住居もみつかっていない。従来の集落内貝塚にくらべ、けた違いの大きさであること、出土する貝種が河口付近の泥干潟(→ 干潟)でとれるカキ、海に面した砂干潟でとれるハマグリにほぼ限定されることなどもあわせて、居住地にともなう「ムラ貝塚」ではなく、「ハマ貝塚」の極端に大きなものと考えられている。
興味深いのは、貝塚背後の砂地から焼き石を投入し、水を沸騰させて貝のむき身をとった木枠付き土坑(どこう)や、焚き火跡(たきびあと)、木道などが確認されたことである。これらの施設は、海岸線に並行して当時形成されていた幅30〜40mの砂州の内側からみつかっており、処理済みの貝殻はこの砂州をこえて外海にすてられ、巨大な貝塚が堆積(たいせき)されたと推定されている。
長期にわたり専業的、かつ大規模に生産された大量の干し貝は、近隣集落への供給にとどまらず、内陸地域へも交易されたらしく、縄文時代の生産・社会的分業を考えるうえで重要な遺跡といえる。なお、貝層南側から発見された杭(くい)にのこるカキの付着状況から、当時すでにこうした杭を養殖に利用していた可能性も指摘されている。2000年に国の史跡に指定された。